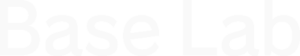ベトナム政府が2026年7月からハノイ中心部でガソリンバイクを全面的に禁止する方針を示したことが、市民生活に大きな波紋を広げている。現在、ハノイには約700万台のバイクが走っており、その多くが大気汚染の主要因とされている。世界保健機関(WHO)によれば、同国では大気汚染が年間7万人もの死亡原因になっており、排ガス対策は喫緊の課題とされる。しかし、急激な規制強化には市民から懸念や反発の声が相次いでいる。
今回の措置は首相指令第20号に基づくもので、2026年7月1日から環状道路1号線内でガソリンバイクの走行が禁止され、2028年には環状道路2号線、2030年には3号線へと拡大される予定だ。さらにホーチミン市でも同様の規制が検討されており、政府は2030年までに国内の自動車の30%、バイクの22%を電動化する目標を掲げている。
市民の間では賛否が分かれる。すでに電動バイクに切り替えた人々は空気改善への期待を寄せる一方、多くの人はインフラや生活への影響を不安視している。電力供給の不安定さや充電設備の不足、公共交通の未整備など、実施に向けた課題は山積みだ。特に、配車サービスや宅配業に従事する低所得層の人々にとっては、バイクが唯一の生計手段であり、突然の規制は「生活の基盤を奪う」との声も強い。ハノイ市当局は登録費用の全額免除や最大500万ドン(約19万円)の補助金を検討しているが、電動バイクの価格は平均1000ドル前後と依然として高額であり、十分な支援策とは言い難い。
また、政策の裏に国内最大財閥ビングループとその電動車ブランド「ビンファスト」の利権が絡んでいるのではないかとの疑念もくすぶっている。同社は電動バイクやEVタクシー、充電インフラを展開しており、政策の最大の受益者になると見られている。SNS上では「環境対策を口実にした産業政策だ」との批判も目立つ。
専門家は、大気汚染対策にはより広域的かつ総合的な戦略が必要だと指摘する。実際、ハノイの微小粒子状物質(PM2.5)の半分は市外の農業焼却やリサイクル村から発生しており、都市部だけを規制しても抜本的な改善にはつながらないとの見方が強い。
このバイク禁止政策は、環境改善という大義と社会的混乱のリスクの間で揺れている。短期間での電動化推進は、電力供給やインフラ整備、生活支援策など、幅広い準備が不可欠である。実施が強行されれば、都市交通や市民生活に大きな混乱をもたらす可能性が高く、ベトナムにとって“急ぎすぎた緑の転換”となる危険性がある。政府がどのように現実的な施策へと調整していくのかが、今後の大きな焦点となる。